白隠禅師 《夜船閑話》
| 本文その一 わしが初めに禅に参じた日、心に誓って勇猛の信心をふるいおこし、不退転の道を求める情(こころ)をふりおこし、精錬刻苦すること二、三年、ある夜、たちまち心から何かが抜け落ちた。 それまで抱いていた多くの疑惑が根本から氷のとけるようにとけ去った。 長い、長い間生死をくりかえして来た過去世に積んだ業の根が、根底からなくなってしまった。 その時わしは思った。 「道というものは自己をはなれて遠くにあるものではない。 古人は道を求めて二十年も三十年も苦労したというがなんともおかしなことよ」と。 それから数ヶ月、手の舞足の踏むところを知らずというよろこびがつづいた。 しかるに、その後、毎日の自分のありようをふり返ってみると、動と静の二境が全く調和していない。あるいは行き、あるいはとどまるというありようにしても、さっぱり洒脱自在ではない。 そこでわしは思った、「勇猛精進して修行に精彩を放ち、重ねていま一度、大死一番しょう」と。 そこで歯を喰いしばり、両眼をかっと見ひらき、寝食ともに廃せんとするほどの修行をしたのであった。 それからひと月もたたぬうちに、心火逆上し、肺臓が焦げ枯れて、両足は氷雪の中に入れているように冷たくなり、両耳はまるで谷川のそばにでもいるようにざわざわと鳴った。 肝臓も胆嚢も弱り果て、立ち居振舞いがおどおどとなり、心神疲労し、寝てもさめても幻影を見、両脇の下には冷汗が流れ、両眼には常に涙がたまるという有様になった。 そこで諸方あまねく訪ねて明眼の師家につき、広く名医を尋ねたけれども、百薬投じていささかも効果なしという状態であった。 ある人が云うのに、「山城国の白川村の山中の巌窟の中に住んでいる者がある。 世間ではこの人のことを白幽先生と呼んでいる。 年齢は百八十歳から二四〇歳ぐらいは経ている。 人里から三〜四里も離れたところに住んでいて、人に会うことを好まない。 行けば必ず走って逃げる。 賢人なのか愚人なのか見分けがつかない。 里の人は仙人だといっている。 噂によれば先年死んだ石川丈山の先生で、天文学にも通じ、深く医の道に達しているということである。 人が礼をつくして問うときは、まれに少し話してくれることもある。 それを後になってよくよく考えてみると、非常に人のためになる言葉であったと思い当たるのである。」と。 そこで宝永七年庚寅の年、正月中旬、ひそかに旅支度をして東美濃の霊松院を出発し、京都の黒谷を越えてただちに白川村に至った。 荷物を茶店に下して白幽子が住んでいる巌窟のありかを尋ねた。 里人ははるかかなた一筋の谷川を指指した。 その水音に随ってはるかに山道に入ってゆく。 行くこと一里ばかりでその流れを横切ると、そこから先は木樵の通う道もない。 そのときひとりの老人に出会ったので、道を聞くと、はるかに雲霧のかなたを指指して、「かなたに黄色に白味がかった一寸余りの四角なものが山気に随って見えたり隠れたりしているであろう。 あれが白幽子の巌窟の戸口に下っている、蘆で作った簾である。」と教えてくれた。 わしはすぐ着物の裾をまくり上げて登って行った。 険しい巌を踏み、ツタや葛を押し分けて行く。 氷雪はわらじを噛み、雪や露に衣は濡れた。 油汗を垂らしてようたくかの蘆の簾のところにたどりつくと、風致の清らかなことは形容を絶し、まことに人間界とは思えぬほど、心魂は震え恐れ、肌は粟立つといったありさまであった。 しばらく巌の根によりかかって息を数えること数百、しばらくあって衣を振って塵を落とし、襟を正して、おずおずと腰をかがめて簾の中をいかがうと、おぼろげながら白幽子が眼を軽く閉じて端座しているのが見えた。 真っ黒な髪が膝まで垂れ下がり、朱のような赤い顔の美しいこと棗のようである。 大きな布のような上着をまとい、軟らかな草の敷物の上に座している。 巌窟の中は五、六尺四方くらいで、、生活の道具というべきものは何もない。 机上にはただ中庸と老子と金剛般若経とが置いてある。 わしは礼儀をつくしてつぶさに病気の原因を告げ、助けて頂きたいと請うた。 しばらくして白幽子は眼をあけてじっとわしの方を見て、静かに告げて言うのに。 「わしはこの山の中にいて半分死んでいるような無用人である。 木の実や栗などを拾って食い、鹿のたぐいを友として寝る。 この他さらに何を知っているだろう。お恥ずかしいことだが、折角遠方からあなたがお訪ね下さってもなにもお答えできないのだ。」と。 わしはそこで、さらに頭を下げてお願いした。 時に白幽子は、ゆったりとわしの手を捉えて、精密に五臓を診察し、九箇の脈処を診察した。 その手の爪の長さは五分ほどもあった。 痛ましげに、また困り果てた様子で告げていうのに、「やれやれ、座禅観法の度が過ぎ、修行が節度を失って、ついにこの重病を発したのだ。そなたの禅病はまことに治しがたい。もし針と灸と薬の三つのものを頼みとしてこの病を治そうとするのなら、中国古代の名医扁鵲(へんじゃく)、倉公や華陀が力をつくして心配しても奇効をあらわすことはできない。 そなたは今すでに禅観が過ぎて体を破っている。つとめて内観の功を積まなかったら、ついには再起不能になるであろう。これはかの入大乗論に、〈地に因って倒るるはまた地に依って起つ〉という言葉の通りである。」と。 わしが言うのに、「願わくは内観の秘訣をお教え願いたい。参禅しつつこれを修めたいと思います。」と。 白幽子は粛然として態度を改め、ゆったりとして告げて言うのに、ああ、そなたのような人はまことに問うことを好むの士である。それではわしが昔聞いたところを少しばかりそなたに告げよう。これは養生の秘訣で、人のほとんど知らぬことである。怠りなく修行するなら、不思議な効能をあらわすであろう。また長生きもできるであろう。 〜本文その一終わり〜 |
|
本文その二 |
|
| それ大道というものは分かれて二つとなる。 それが陰陽で、この二つが和合して人間が生まれる。 その人間が天から受けた元気が黙々として体中をめぐり、五臓につらなり、経脉にめぐる。 衛気(将師ともいうべき気)と営血(士卒ともいうべき血液)とが互いに昇降循環すること一昼夜におおよそ五十回である。 肺臓は雌の臓器であって横隔膜の上に位置し、肝臓は雄の臓器であって横隔膜の下に沈んでいる。 心臓は太陽であって上部に位置し、腎臓は太陰で下部に位置する。五臓に七つの神気があり、脾臓と腎臓に各々二つの神気を蔵している。 吐く息は心臓と肺臓より出で、吸う息は腎臓と肝臓に入る。 一呼毎に脉が三寸行き、一呼毎に脉が三寸行く。 一昼夜に一万三千五百の気息があり、脉は一身を巡ってゆくこと五十回。 火は軽く浮くもので常に昇ることを好み、水は重く沈むもので常に下の方へ流れ行こうとする。 もし人が、この道理を察せず、観照が節度を失い、志念が度を過ぎる時は、心火が燃えて衝き上がり、肺臓を焼き焦がす。 母なる肺臓が苦しむ時は、子である腎臓が衰滅する。 母と子と互いに疲れ傷んで、その結果五臓が疲労し、六腑が犯される。 四大すなわち地水火風の四大元素の調和が破れて増減を生じ、四大の各々に百一の病を生ずる。 こうなると百薬もききめはなくなる。 多くの医者はすべて手をこまねいて、何とも言いようがないようなことになってしまうのである。 思うに、生を養うということは、国を守るようなものである。 名君や聖王は、常に心を下々の方に専らにし、暗君や凡庸な君主は常に心を上の方にのみほしいままにする。 上の方にほしいままにする時は、九卿が権勢に誇り、百官が君主の寵をたのんで、民間の苦しみをかえりみることがない。 野にある者は顔色青ざめ、国に餓死するもの多い。 賢人、良臣はひそみかくれ、臣民は怒り恨む。 諸侯は離れそむき、多くの異族は競い起こって叛旗をひるがえし、ついに民衆を苦難におとし入れ、国体は永く断絶するに到るのである。 心を下々の方に専らにする時は、九卿は倹約を守り、百官は倹約につとめて、常に民間の労役を忘れることがない。 農民は余剰の粟を持ち、農婦には余剰の衣服がある。 多くの賢人が来たってこの国の人となり、諸侯は恐れて帰服し、民肥え、国強く、法令に違背する庶民はなく、国境を侵す敵国はない。 国のうちに戦いの銅鑼のひびきなく、人民は剣戟の名も知らぬようになる。 人間の体もまた同様である。 道に適した至人(しいじん)は常に心気を下半身に充実せしめる。 心気が下半身に充実している時は、喜・怒・憂・思・悲・驚・恐の七情による病が内に動くことなく、風・寒・暑・湿の四つがもたらす邪気も外より窺うことを得ない。 体の備えは充分となり、心神すこやかである。 口は薬の甘いも酸いも知らず、身はついに鍼や灸の痛痒を受けない。 しかるに凡人どもは常に心気を上方にほしいままにしている。 心気を上方にほしいままにする時は、佐寸すなわち肺臓の金を侵して、五官すなわち眼・耳・鼻・舌・身の各器官が萎縮して疲れ、父母妻子兄弟の六親すべて苦しみ恨むにいたる。 このゆえに漆園すなわち中国古代の思想家荘子が言っている、「真人の息は踵でやり、衆人の息は喉でやる」と。 |
|
| 朝鮮の名医許俊は言っている、「気が下焦(げしょう)すなわち膀胱の上あたりにある時は、その息が長くなり、気が上焦(じょうしょう)すなわち心臓の下にあると時は、息が短くなる」と。 中国近代の医家上陽子(じょうようし)は言っている。 「人には真にして一なる気というものがある。それが丹田(臍の下)の中に降下する時は、一陽が生ずる。 もし人、その陽が生じた兆しを知ろうとするなら、暖気が生じてくるのをたよりとせよ。 おおよそ生を養うの道は、上部を常に清涼ならしめることが必要であり、下部を常に温暖ならしめることが必要である」と。 それ経脉の十二、すなわち心・肺・脾・腎・胆・胃・大腸・小腸・膀胱・心包・三焦・の十二個所にあるそれぞれの経脉は、支の十二、すなわち子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二支に配し、これが月の十二に応じ、時の十二に合っしている。 六交すなわち六つのが劃線(かくせん)が、正卦(せいけ)・変卦(へんけ)の十二の劃線となって循環し一年を全うすることになる。 五陰が上におり、一陽が下におるのを、易の卦では地雷復(じらいふく)と言うが、これは季節でいうと冬至の候である。 これは「真人の息は踵でやる」と言うのに当たる。 三陽が下におり、三陰が上におるのを、地天奉と言う。 正月の候である。 万物が発生の気を含んで、百花が春の恵みを受ける。 これは至人が元気を下方に充実せしめる形象である。 人がこれを得ると、体の構えが充実し、気力勇壮である。 五陰が下におり、一陽が上にとどまるのを山地剥(さんちはく)と言う。 九月の候である。 天がこれを得る時は、林苑みどりの色を失い、百花みな枯れ落ちる。 これは「衆人の息は喉でやる」と言う形象である。 人これを得る時は、姿形が枯れ痩せ、歯が揺らいで抜け落ちる。 このゆえに延寿書に言っている、「六陽ともに尽きてしまう時は、この人は全陰の人で、死にやすくなる。 それゆえ元気を常に下方に充実せしめることが生を養う上で最も重要であることを知るべきである」と。 |
|
昔、呉契初(ごけいしょ)という者が石台先生に見(まみ)え、斎戒して練単丹の術を問うた。 先生が言うのに、「わしには元玄真丹という秘法があるが、上々の機根の者でなくてはこれを伝えることはできない。 古代に黄成子という者がこれを黄帝に伝えた。 黄帝は三七二十一間斎戒してこれを受けた。 それ大道の他に真丹はなく、真丹の他に大道はない。 五無漏法(ごむろほう:迷いが無くなる五つの方法)というものがある。 汝の六欲すなわち色欲・形猊(ぎょうみょう)欲・威儀姿態欲・言語音声欲・細滑欲・人相欲を去り、眼・耳・鼻・舌・身の五官が各々その職分を忘れる時、渾然たる本源の真気が彷彿として目の前に充満するのである。 |
 |
| これは、かの大白道人の言う「我が天をもって、事(つか)うるところの天に合する」ものである。 孟子のいわゆる浩然の気、これをひきいて、臍輪・気海・丹田の間におさめて、歳月を重ねてこれらを守り通し、これを養って育てあげておいて、一朝、その仙薬を練るかまどをひっくり返すなら、その時は、内外、中間、四方八方、宇宙全部ひっくるめての大仙薬となる。 この時はじめて、自己は天地に先立って生まれず、虚空に遅れて死なぬ、というていの真実長生の大神仙であることを覚るであろう。 これを真実仙丹を練ることのできた時節とするのである。 なんで風に乗り、霞にまたがり、地を縮め、水を渡るといった、瑣末な幻術を本懐とするものであろうぞ。 それは、大海をかきまわして酥酪(そらく:バターやチーズの類)とし、大地を変じて黄金となすていのものである。 昔の賢人が言うのに、「丹は丹田である。液は肺液である。肺液を丹田に還す、このゆえに金液還る丹と言うのである」と。 〜 本文その二おわり 〜 |
|
本文その三 |
|
| わしは言った、「謹んでご命令を聞きました。 しばらく禅観を取り出して、病を治すことに専念いたしましょう。 ただ心配なのは、明の名医李士才(りしさい)の言う、〈*清い降〈せいごう〉に偏するもの〉になりはしないかということであります。心を一処に制すると、気血があるいはとどこおることになりますまいか」と。 白幽子は微笑して言うのに、「そんなことはない。 李士才が言っているではないか。 火の性は炎上する、それゆえこれを下らしめなければならなぬ。 水の性は下るものである。 それゆえこれを上ぼらしめなければならぬ。 水が上がり、火が下る、これを名づけて〈交〉という。 それが交わるのを〈既済:きせい〉とする。 交わらないのを〈未済:みせい〉とする。 交は生の形象であり、不交は死の形象である。 李士才が「清降に偏なり」と言ったのは、朱丹渓の教えを学ぶ者の弊害を救わんがためである。 古人が言っている、『相の火が上がり易いと身中が苦しむことになる。 水を補うのは火を制するためである』と。 思うに、火は君・相の二義がある。 君の火は上方におって静をつかさどり、相の火は下方におって動をつかさどる。 君の火はこれ一心の主である。 相の火は輔佐の宰相である。 思うに相の火には二種ある。 いわゆる腎臓と肝臓がそれである。 肝臓は雷に比せられ、腎臓は龍に比せられる。 このゆえに、龍を海底に帰らしめれば、迅雷の発することはない。 ただし雷を沢(たく)の中に蔵(かく)しめるなら、龍が昇騰することは決してないであろう。 海にせよ、沢にせよ、いずれも水であるから、相の火の上りやすいのを制するのである。 また言うのに、心が煩い労する時は、虚すなわち体調すべて負となり、心が熱する。 心が虚となる時は、これを補うには、心を下して腎に交える。 これを(補:ほ)と言う。 これは既済の道である。 *清い降〈せいごう〉に偏するもの・・・寒冷の薬をもって心火を降下させすぎること そなたは先に心火逆上にしてこの重病を発した。 もし心を降下させなかったならば、たとい欲界・色界・無色界のすべての秘密の行を修行しつくしても、再起することはできぬであろう。 かつまた、わが姿形が道家の人に類しているので、仏教者とは違うとするか。 これは禅である。 他日そなたが悟りをひらいた時には、呵々大笑することであろう。 それ観というものは、無観をもって正観とする。 多くの観あるものを邪観とするのである。 先にそなたは多観のためにこの重症になった。 今これを救うのに無観をもってするのが一番よいのではないか。 そなたがもし、心の炎、意の火という心火上昇を収めて、丹田足心の間においたならば、胸の中は自然に清涼となり、ああでもないこうでもないと思いめぐらすことが一点もなくなり、分別意識や心情の波は一滴もなくなるであろう。 これが観音経にいう「真観清浄観」である。 しばらく禅観を放り出して、などと言ってはならない。 仏が言われている、「心を足心におさめてよく百一の病を治す」と。 阿含経に「酥(乳製品)」を用いる法が説かれており、心の疲労を救うのにもっとも効きめがある。 天台大師の摩訶止観には病因を論ずること、はなはだ意をつくしている。 療治法を説くこともはなはだ精密であり、十二種すなわち、上・下・焦・満・増長・滅壊・冷・暖・衝・持・和・補という息がある。 これによって多くの病を治すのである。 また、心を臍の上におき、豆粒のごとく見る法がある。 その大意は、心火を降下して、丹田および足心に収めるのを肝要とする。 それはただ病を治するのみではない。 多いに禅観を助けるのである。 摩訶止観の中に〈繋縁:けえん〉〈諦真:たいしん〉の二つの〈*止〉が説かれている。 諦真とは実相の円観(この世の姿は相対がそのまま絶対、絶対がそのまま相対と見ること)である。 繋縁とは心気を臍輪・気海・丹田の間に収めるのを第一とする。 行者これを用いれば、大いに利益ある。 *止 : 心を一点に集中し静止せしめること 昔、永平の開祖道元禅師が大宋国に入って天童山で如浄禅師を礼拝相見した。 道元禅師がある日、密室に入って如条浄の教えを請うた時、如浄は言った。 「道元よ、崇拝の時、心を左の掌の上に置くべし」と。 これが天台大師の云う〈繋縁止〉の大略である。 天台大師は始めこの〈繋縁内観〉の秘訣を教えて、その兄鎮慎〈陳鍼:ちんしん〉の重病を万死の中から助け救ったことは、くわしく天台小止観の中に説かれている。 また白雲和尚が言っている、「我つねに心を腹の中に充たしめている。 衆徒を正し、率い、客を接し、機に応じ、小参〈臨時の説法〉や普説〈師家が一般大衆に説法すること〉の説法において縦横無尽にできるのもこのためである。 老いてからは殊に利益多きを覚える」と。 まことに尊ぶべきことである。 これは中国の医書『素問:そもん』に見える、「恬澹(てんたん)虚無であると真気がこれに従う。 精神を内に守るなら、病がどこからくるだろうか」という言葉に本づかれたものであろうか。 その内に守るという要点は、元気をして一身の中に充満せしめ、三百六十の骨、八万四千の毛穴に至るまで、髪の毛一本ばかりも欠けるところがないようにすることが肝要である。 これこそ、生を養う至極の要点であることを知るべきである。 八百歳の長寿を保った中国の仙人彭祖(ほうそ)が言っている。 「精神を和げ、心気を導くやり方は、密室に閉じこもり、床をとり、敷物をあたため、枕の高さ二寸五分、体をまっすぐに仰向けに伏し、眼をつむって、心気を胸の中におさめ、水鳥のやわらかな羽毛を鼻の穴にかざしても動かぬほど静かな息を三百息し、耳は何も聞かず、眼は何も見ない。 このようにする時は、寒暑も身体を犯すことはできず、蜂やさそりも毒害を加えることができない。 こうして三百六十歳になれば、真人に近い」と。 また宋の文人蘇東坡(そとうば)が言っている。 「腹が減ってから食事し、腹一杯にならぬうちに止める。 散歩逍遙し、つとめて腹を空にする。 腹が空になった時に静室に入り、黙然と端座して出る息、入る息を数えよ。 一息より数えて十息に到り、十息より数えて百息に到り、百息より数えて千息に到る。 その時この身は山がそびえるようになり、この心は寂然として虚空と等しくなる。 かくのごとくなることを久しくして、一息おのずからとどまる。 息が出でず、入らざる時、この息は八万四千の毛穴から雲霧がむらがり起こるような有様となり、長い長い前世からの諸病が自然に除かれ、多くの障りが自然になくなることを明らかに悟るのである。 たとえば盲人がたちまちに眼をひらくがごとくである。 この時もはや人に自分の行く道を尋ねる必要はなくなる。 ただ普通の言語は省略して、自分の元気を長く養うことが大切である。 このゆえに言う。 「目の力を養う者は平生目を閉じ、聴力を養う者は平生余分なことは聴かず、心気を養う者は平生沈黙する」と。 〜 本文その三 終わり 〜 |
|
本文その四 |
|
| わしは言った、「酥を用いるの法をお教え下さるまいか」と。 白幽子は言った、「修行者が座禅している最中に、体の調子が悪く、心身ともに疲労したと自覚したならば、心を奮い起こしてまさにこの理念をなせ。 たとえば色も香りも清浄な軟酥(やわらかなバターのごときもの)の、鴨の卵ぐらいの大きさのものが頭上にのっていると想うだ。その気味はきわめて微妙で、丸い頭の鉢全体をうるおし、ひたひたとうるおしながら下ってきて、両肩および両の臂、両乳、胸の中、肺臓、肝臓、腸、胃、脊梁骨、臀骨と次第にうるおしながら注いでゆく。 このとき胸の中の五臓六腑のとどこおり、疝、癖、塊痛が心に随って降下することは、水が下方に注いでゆくようなもので、歴々として音を立て、全身を巡り流れ、双脚をうるおし、暖かにし、足の裏に至ってとどまる。 修行者は二たび、三たびこの観をなすべきである。 かのひたひたとうるおし下るところの余流が、積もり、湛えられて暖めひたすことは、あたかも世間の良医が種々の薬物を集め、これを煎じた湯を浴盤の中へ汲み入れ湛えて、わが臍輪から下を漬けひたすがごとくである。 この観想をなす時、心に思うところが現実となって、鼻はたchまち世にもまれな香気を嗅ぎ、体はにわかになんともいえず軟らかな感触を受ける。心身調って快適であることは、二、三十の時よりもはるかに勝っている。 この時、五臓六腑のとどこおりはすべて消失し、腸胃は調和し、知らぬ間に肌につやつやとした光沢が出てくる。 もしこの修法をつとめて怠らなかったなら、どんな病でも治らぬということはない。 どんな徳行でも積まれないということはない。 どんな仙術でも成就しないということはない。 その功能のあらわれるのに遅速があるのは、修行者の精進が精であるか粗であるかによるのみ。 わしのわかい頃は多病で、そなたの病の十倍も悪かった。 医者という医者がみんな振り向いてもくれなかった。 あらゆる手段を用いたが救うすべはなかった。 そこで、上下の神様に祈り、天仙の冥助(めいじょ=眼に見えない助け)を乞い願った。 そしてなんという幸せか、計らずもこの軟酥の妙術を伝授されたのである。 わしは喜びに堪えず、怠りなく精進修行した。 すると一ヶ月もたたぬうちに多くの病が大半快癒してしまった。 それより以来ずっと、身も心も軽々としている。 馬鹿のようになってしまい、毎月の大小は分からず、四年に一度の閏も忘れ、世の中のことを次第に忘れ、世間の人の欲望も、ならわしも、いつしか忘れ去ったのである。 わしの年が今年何十歳であるかも知らないのだ。 先頃、あるご縁で、若狭の山の中に入りこんで三〇年ばかり経ったが、世の人はそのことを誰も気がつかない。 過ぎこし方をかえりみるに、あたかも中国の廬生(ろせい)が邯鄲の茶店で眠り、一生をすごした夢を見てさめてみれば、茶店の主人の煮ていた黄梁(おうりょう)はまだ半煮えであったという故事のごとくである。 今、この山中の人のいないところで、この枯れ衰えた骨だらけの体に、太布の単衣をわずかに二、三枚かけ、厳冬の寒さが綿をもくじくような寒さであっても、老いぼれた腸を寒さでいためることはない。 山の木の実もなくなり、穀物を口にせざること数ヶ月に及んでも、ついに凍えたり飢えたりすることがないのは、皆この内観の力ではないか。 わしは今そなたに、一生用いても用い切れないほどの秘訣をお教えした。 この外何も言うことはない、と言って、眼を閉じて黙座した。 わしもまた、涙を浮かべて別れの挨拶を申し上げたのであった。 静かにゆっくりと洞窟の口元を下れば、木末にわずかに落日がかかっている。 折しもカラコロと下駄の音が山や谷にひびいた。 驚き怪しんで、恐る恐るうしろを振り返ると、はるかかなたに白幽子が巌窟を離れて自らを送りに来てくれているのが見えた。 すなわち言うのに、、「人跡未踏の山道で、西も東も分かるまい。恐らくは道が分からなくなるであろう。 この老人がしばらく道案内をして進ぜよう。」と言って、大駒下駄をはき、痩せ鳩杖をついて、岩を踏み、険しい道を登ること、まるで平地を行くようで、談笑しつつ先立って歩いた。 山路はるかに一里ばかりも下って、かの谷川のところに達して、さて言うのに、「この流れに随って下ったら、必ず白河村に出だろう。」と。 互いに別れがたい思いで別れたのであった。 羨ましいとも思い、また敬服もした。 死ぬまでこれらの人についてゆくことができないのを自ら恨みとしたのであった。 さて、おもむろに帰庵して、時々刻々かの内観法をひそかに修めること、わずかに三年に満たざるうちに、これまでの多くの病が薬も用いず、鍼灸の助けもかりずに、いつとはなしに除かれ治ってしまった。 ひとり病が治ったばかりではない。 これまで手足もつけられず、歯も立たなかったほどの難信、難透、難解、難入の公案が、根底から透過できて大歓喜を得ることおおよそ六、七回。 その余の小悟で喜びに手の舞い足の踏むところを忘れたことは数を知らぬほどである。 南宋の大慧宗杲禅師が言われた「大悟十八度、小悟数を知らず」と言うことをはじめて知り、まことだと納得がいったのである。 わしは昔、二、三枚の綿入れを着ていても、足の裏がいつも氷雪に浸しているようであったが、今は真冬のきびしい寒さの中でも、綿入れも着ず、炉火もいらず、年はもう七十を越えたが、これと言うほどの病気もないのは、かの神術のおかげであろうか。 白隠が死にかけの息のきれぎれに、でたらめの話を記して、他人を欺すのであろうなどと言ってはならない。 これは生まれながらにして英明の素質あり、一言のもとに領解できるような俊才のために設けrのではない。 わしのように愚鈍であり、病に苦しんでいる人が、読んで子細に観察したならば必ず少しは補いになると思ってのことである。 唯ある別人が手をうって大笑されるのを恐れるのみ。 それは何故か。 「馬が枯れた豆殻を咬んで、まぁ、昼寝の枕に騒がしいことよ」と、貴山谷詩集に言うではないか。 宝暦七年正月二十五日 |
|
Page top
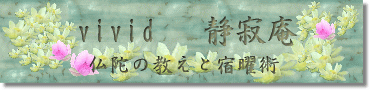 初心者のための仏教学びのサイト
初心者のための仏教学びのサイト 